※この記事は2025年8月9日に追記・修正いたしました。
「野球?別に…」そう思ったあなたにこそ観てほしい。 ケビン・コスナー主演の不朽の名作『フィールド・オブ・ドリームス』(1989年)は、野球に全く関心がなくても、心の奥底に響く普遍的な感動を約束する一本です。 私、電八もプロ野球には正直、ほとんど関心がありません。しかし、本作は単なるスポーツ映画の枠を超え、父と子の絆、そして家族の温かい繋がりを描いたヒューマンドラマの最高峰に位置します。観終わった後には、「なぜ人は夢を追い続けるのか」「家族とは何か」という問いに、きっとあなたなりの答えが見つかるでしょう。この記事では、その魅力を余すところなく解説します。AmazonプライムビデオやU-NEXTで今すぐ視聴可能です。」
しかし、『フィールド・オブ・ドリームス』は、単なる野球映画ではありません。物語の中心にあるのは父と子の絆、そして家族とのつながりを描いたヒューマンドラマ。野球を愛する人の気持ちや、その背景にある夢や情熱が自然と心に伝わり、観終わった後には「なぜ人は野球に夢を重ねるのか」という問いに少し近づけます。
さらに、妻や娘との家庭の温かい関係も丁寧に描写されており、家族映画としての完成度も非常に高い作品です。野球ファンはもちろん、スポーツに関心のない人にも響く普遍的なテーマが詰まった、映画史に残る名作といえるでしょう。
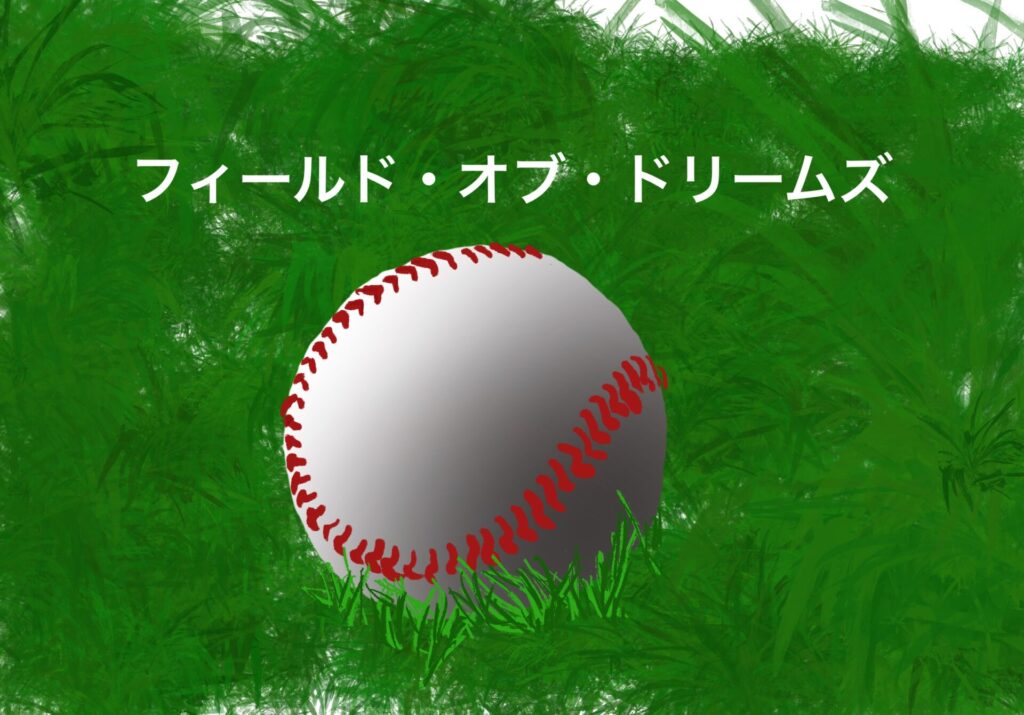
作品概要「フィールド・オブ・ドリームス」

1989年公開のケビン・コスナー主演、フィル・アルデン・ロビンソン監督作品。
ウイリアム・パトリック・キンセラの小説『シューレス・ジョー』が原作で、主人公レイ・キンセラは原作者の祖父的な設定らしい。
1960年代をキーワードに「良きアメリカ」を描いたファンタジー作品です。
※注意:この記事にはネタバレが多分に含まれています。作品をご覧になっていない方にはオススメできません。
ざっくりあらすじ

トウモロコシ農場を経営しながら、妻と娘と3人家族で無難に生きているレイはある日、トウモロコシ畑で”声”を聴く。
その”声”は「お前が作れば、やってくる」と言っていた。
衝動に任せてみると「トウモロコシ畑をつぶして球場を作れば”シューレス・ジョー”がやってくる」というのが分かる。
今まで冒険的なことを何ひとつしてこなかったレイは思い切って”声”に従って畑をつぶして球場を作る決心をする。
そして、奇蹟が起こり始める―――。
野球が分らなくても楽しめる。

基本的に人間ドラマなので野球が分らなくても楽しめます。
- 野球選手の幽霊たちが陽気で笑えます。
- 謎解き要素があります。
- カリンがかわいいです。
- 景色が美しいです。
など、野球に言及した映画ではなくテーマもアメリカの時代背景や思想、そして家族の絆などが中心でロードムービー的に分かり易く見せていく作りになっています。
叶わなかった夢を実現させる

主人公レイ、テレンスマン、球場に現れたシューレス・ジョーを含む選手たち、そしてレイの父親。
彼らはみんな夢を叶えられなかった人々として描かれます。
その中で唯一、レイだけは夢を叶えることが出来て、しかも上記に挙げた人物と妻と娘に応援されます。
難しい決断の時、必ずそばにいる誰かが背中をそっと押してくれます。
人から見たらどんなにバカげた夢だったとしても、夢に向かって踏み出す自分のそばに必ず応援してくれる人がいます。
全体としてものすごくやさしく夢を応援する映画になっています。
60年代がキーワード

1960年代後半から1970年代にかけてのアメリカは、ベトナム戦争の影響で社会が大きく揺れた時代でした。戦争により多くの兵士が命を落とし、帰還した者たちは心身に深い傷を負いました。また、戦費が経済を圧迫し、国民は生活の厳しさを感じ、政府への不信感が広がりました。戦争の暗い現実が国全体に漂い、国民は希望を見出すのが難しい時代となりました。
このような中で反戦運動が活発化し、若者たちを中心に「ラブ&ピース」を掲げたヒッピー文化が広がりました。彼らは戦争に反対し、愛と平和を訴える新しい価値観を示しました。ヒッピーたちは既存の社会秩序に反発し、自由を追求するライフスタイルを実践しました。また、音楽やファッション、文学を通じてカウンターカルチャーが生まれ、1969年のウッドストック・フェスティバルはその象徴となりました。
同時に、公民権運動も広がり、マイノリティが人種差別と戦い、平等な権利を求めました。1964年に公民権法が成立したものの、社会にはまだ根深い差別が残っていました。こうした運動のリーダーたちは、社会の変革を目指し、国民の意識を変えていきました。

文学やアートにも、この時代の精神が反映されました。サリンジャーの作品などが若者たちに影響を与え、彼らが社会運動に参加するきっかけとなりました。若者たちは、これまでの価値観に疑問を持ち、新しい生き方や考え方を模索していました。
1970年代に入ると、ベトナム戦争は終息に向かいますが、その傷跡は深く、戦後も社会の分断や経済的な停滞、政治的不信が残りました。それでも、多くのアメリカ人は、この時代の試練を経て新たな未来を模索し、社会の変革を求める力は次世代へと引き継がれていきました。この時代は、アメリカが転換点に立たされた重要な時期であり、戦争の影響や社会運動がその後のアメリカ文化に大きな影響を与えたのです。

学校の体育館での「悪書追放運動」のシーンでは、この辺りのことを描いています。
テレンスマン(サリンジャー)の本を悪書と言っていた夫人に対してアニーは「50年代を2回繰り返して70年代に飛んだんでしょ?」と言っていたのは、偏見や差別の時代を乗り越えてきたはずなのに、愛を説いていた作家の本を燃やせというのは、偏見や差別の時代しか知らないからだという主張だったのです。
金曜ロードショー版が好き。

映画DVDには実は一本の作品で〇〇版というのがあります。(ディレクターズカット版とか)
この「フィールド・オブ・ドリームス」には金曜ロードショー版というのがあります。この金曜ロードショー版が自分にとっては最高です。
地上波番組用の編集なので吹き替え版となっています。
吹き替え版はいくつかバージョンがあるのですが、金曜ロードショー版の声優陣が一番キャラクターにフィットしているように感じます。
そして何より翻訳がいいです。最高のセリフになっていると思います。
夢を追い続けた者たちの“あと一歩の苦しみ”──『フィールド・オブ・ドリームス』に描かれる切ない希望

『フィールド・オブ・ドリームス』では、叶えられなかった夢を抱えた人々が、レイが作った球場に次々と集まってきます。彼らはただの幽霊ではなく、かつて夢に手が届きそうだった“あの瞬間”を逃した人たちです。
その象徴的存在が、アーチボルト・“ムーンライト”・グラハム医師。彼は現実世界では町の人々に愛された医師で、人生に満足していたように見えます。しかし彼にも忘れられない瞬間がありました。
──それは、メジャーリーグでたった1試合、しかも1イニングだけ出場しながら、一度も打席に立てなかったという悔しさ。
ほんの少し手を伸ばせば届くはずだった夢。その夢が指の先をすり抜けていく感覚は、ただ夢を持っていたからこそ感じる苦しみとも言えるでしょう。

「もし奇跡が起きるなら、一度でいいからメジャーの試合でバッターボックスに立ってみたい」──グラハムのそんな願いが、まさに映画の中核となっています。
このような“夢を諦めきれない人たち”が集まってくる場所が、主人公レイが建てた球場なのです。そして実は、レイ自身も心の奥に夢と痛みを抱えている一人。彼の再生と和解の物語もまた、観る者の心を静かに打ちます。
テレンス・マンのセリフ

テレンス・マンは原作を読むと分かるのですが、実在の作家サリンジャーがモデルです。
原作ではそのままサリンジャー本人として描かれています。
レイが義理の兄に農場に作った球場を売るように迫られているシーンでのセリフがいいです。もちろん金曜ロードショー版のが最高です。
以下、本編よりセリフを引用。
レイ、人々はやって来るよ。
みんなこのアイオワへ。
たぶん理由もわからずに 見えない糸に引かれて 大勢の人々が集まってくる。
入り口に立って、子供のように無邪気に昔を懐かしみ。
もちろん君らは笑顔で客を迎えるだろう。
観戦料は20ドル。
みんなためらいもせずに出すさ
金は持ってるんだ。
無いのは安らぎだ。
やがてスタンドに出てくるとみんなシャツの袖をまくり暑い午後が始まるんだ。
何と言ってもそこは最高の席だ。
ベースラインがすぐ近くに見える。
子供の頃、よくそこに座ってヒーローの名を叫んだもんだ。
試合を見ているとまるで魔法の水に浸っているような気持ちになる。
思い出が次々と押し寄せてそいつを払いのけるのにひと苦労だ。
人々はきっとやってくる。
長い年月、少しも変わらなかったのはこの野球だけだった。
アメリカはロードローラーのようにめまぐるしく、黒板のように様相を変える。
消してはまた描き。
だが、野球は人々と共にあった。
このグランドも このゲームも 我々の過去の一部だ。
かつての良き時代を思い起こさせ、甦らせてくれる。
ああ、人でいっぱいになるぞ。
必ずやってくるとも。
「フィールド・オブ・ドリームス」金曜ロードショー版のセリフより引用
そして彼はシューレス・ジョーにトウモロコシ畑の「向こう側」へ招待されます。
笑い声と共に消えていきます。
彼は「向こう側」で何を見て、そして何を書いて本にするのか?それはあなたの想像にお任せいたします。
そして彼は、このことで「作家」としての自分を取り戻します。
つまり、ここでテレンスマンの「苦痛」が癒されるのです。

テレンスマンがトウモロコシ畑に笑い声と共に消えていってしまうと、周囲は静かになり夕暮れ時を迎えます。
うっすらものさみしい感覚に囚われます。
その事から、このシーンでテレンスマンは亡くなったのだという方がよくいらっしゃいます。
電八的にはテレンスマンは亡くなったのではなく、ちゃんと生きて戻ってきてその後大ヒット作を書き上げたと思います。
なぜならば、この今作は無念の内に亡くなった者たちには夢を叶える機会を、現在生きている者たちには夢をかなえるための力を、それぞれ与える再生の物語だからです。
さらにテレンスマンのモデルとなったサリンジャーは2010年まで存命でした。今作が上映された89年はもちろん存命で、翌年90年には50歳も年下の看護師と結婚したのだそう。
亡くなる寸前まで著書に関連した裁判なども行っていて、非常にエネルギッシュな人だったようです。
ますます、「テレンスマン亡くなった説」を信じる気にはなれませんね。
父と子の絆を象徴する「キャッチボール」──アメリカ映画における大切なモチーフ

レイは父親のジョンにわだかまりを持っていました。
そして和解することなくジョンは亡くなってしまったのです。
お互いに本当は野球が好きで、互いに愛しているのに、それを伝えることなく生き別れてしまったのです。
トウモロコシ畑から若返った姿でジョンは帰ってきます。
「なあ、レイ。ここは天国か?」
「いいや、アイオワさ」
それを見たレイは父とのわだかまりを解くチャンスが到来したのです。
「なあ父さん、キャッチボールをしないか?」
ふたりはキャッチボールをします。
お互いの思いを言葉ではなくキャッチボールのボールに乗せて。
夕暮れ時にふたりの語らいはしばらく続きます。
そのままラストシーンへ。
アメリカの映画やドラマにおいて、「キャッチボール」は父親と息子の関係を深める象徴的な行為として描かれることが多くあります。特に『フィールド・オブ・ドリームス』では、キャッチボールが感動的なラストシーンに用いられ、親子の和解と愛情の再確認を示す重要なモチーフとなっています。
近年では、多様性やジェンダー表現への配慮が進む中で、こうした伝統的な父子像を描くシーンは減少傾向にありますが、それでもこの作品のように、親子の関係を丁寧に描いた物語は多くの人の心に響き続けています。
ラストシーンそっくり!!

映画「ペイ・フォワード」でのラストシーンがこの「フィールド・オブ・ドリームス」のラストシーンとそっくりなのです。
両者ともに列をなした自動車がどんどんやってくるのですが、カメラが上昇していくとどこまでもどこまでも自動車のヘッドライトの列が続いているという描写で映画が終わっていきます。
何かこれらの映画に繋がりがあるわけではありません。偶然にしてはあまりにも酷似していてパ〇リだと言われてしまいそうなほど。
けっこうこれで酷評される方もいらっしゃいますが、自分的にはオマージュということで認識しています。(笑)というか真似したらダメならあれもこれもダメ、みたいのいっぱい出てきてしまいます。なによりも製作サイドで問題なかったことなのですからね。
〇今回のまとめ
陽気な幽霊たちがいい。カリンがかわいい。雰囲気がセリフや訳でかなり変わってきます。〇〇版なんてのがあったら試しで観てみるのもありだと思います。
※楽しまないと損だ。
是非ご覧になってください。
無料期間中であれば、無料視聴できますので是非お試しあれ。
▲期間内の解約は0円で、簡単に登録・解約できます▲





コメント